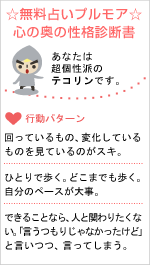|
02.11.01:15 [PR] |

|
05.15.12:32 ブラック・スワン ~映画~ |
作品は、良くもなく悪くもなく。
大々的に宣伝している作品ですが(ローカル番組のシネマ情報でもやっていて驚いた)、興行収入だけを考えればそうしたいのはわかるけど、ホントは観る人を選ぶ作品じゃないかなぁと思いました。
どんな人にでも楽しめる、デートムービーになんか絶対にならないし。。。
主人公ニナ(ナタリー・ポートマン)のキャラが最初から最後まで痛くてたまりません。
あまりに極端で残念で気の毒な人。
そんなキャラを演じきったナタリー・ポートマンはすごいなぁ、格好良かったなぁ!鹿児島の小野さんと同じく「完璧」だと思いましたが、これが主演女優賞を取るほどかと言えば疑問。
そう感じたのはきっと、作品が薄いからだと思います。
サスペンス、ホラー、ヒューマンドラマ、それにバレエの舞台というエンターテインメントの4つの要素があって、サスペンスと特にホラーの部分が余計です。
なんであんな演出にしたのでしょう。
ヘタするとトンデモ映画になりそうだったところを、主演女優がアカデミー賞取れるほどにしたさじ加減は見事!なのでしょうが。。。
まさにナタリー・ポートマンの独り舞台。
「Its my turn!」彼女の中の悪魔と天使が交互に支配する、彼女の独壇場です。
何かを極めようとすると、自分自身との対話が必ず必要になってくるので、生活が健やかでないと、精神はおかしくなっていくでしょう。
ニナは、娘依存の母親がいるために精神を病んでいきます。
彼女は性の衝動を、自慰することで発散しているのですが(振付師にやれと言われたからじゃなく、前からやってたと思われ)、多分、健康的な思春期を送ることができなかったため(友だちと好きな人の話で盛り上がったり、親には内緒の「悪いこと」をしてみたり)、性=悪、と自分自身で決めてしまっています。
その点は、娘をいつまでも子ども扱いする母親の影響でしょう。
ニナが肩甲骨のあたりを掻きむしっているのですが、あれは私もよくやります。
あのあたりは身体のつぼがあって、掻くと気持ちが良いのです。
ニナと同じように、血がでて傷がつくまで掻くときもあり、あの気持ちはよくわかります(^^ゞ
ニナはそれを母親に咎められ、爪を切られるのですが、つまりはあの場面で暗に自慰を咎められているのです。
気の毒なニナ。。。
彼女が指から血を流す幻をよく見るのは、「悪いことをすると母から爪を切られて痛い思いをする」からですね。
また、自分の部屋で自慰するのに、わざわざ母親が入ってこないよう、ドアにつっかえ棒をして・・・というのも悲しすぎます。
彼女は「白鳥の湖」の主役の座をいとめ、プレッシャーでつぶれる前に、すでに十分精神を病んでいたのです。
「不感症の小娘」という悪口は、モンスターペアレントさながらバレエ団に電話をする母親の姿と、山岸涼子先生の漫画に登場するような(「舞姫テレプシコーレ」じゃなく「天人唐草」とか)臆病で繊細な性質をもったニナをみていれば、団員の誰でもが彼女がまだ処女だろうことはわかるから。
また、母親はニナにプリマになってほしいとは本当は思っていません。
娘がバレリーナでいてほしいだけです。
でもニナはそう思っていません。
母親にプリマドンナになることを望まれていると思い込んでいます。
その思い込み、お互いの意思の疎通のなさが悲劇です。
物語は古典的です。
予告で誰もが想像したとおりの話。
まず「キャリー」を思い出しました。
話が進むにつれ、「マルホランド・ドライブ」になるのかと思いきや「世にも怪奇な物語」の「影を殺した男(ウィリアム・ウィルソン)」。
しかし、かくされた意味や物語がどこかにあるのかも?とも思います。
もしかするとウィノナ・ライダー(プリマの座を奪われるバレリーナ)の夢物語では?とか。
でも、ホントに意味はないような気も・・・。
もし、「マルホ」のブルーボックス的なアイテムが登場していたら、少しは物語に厚みがあったんじゃないかなぁと思います。
あくまでも私の主観なので、私の気付かない意味があったのかもしれません・・・。
ニナの持つ二面性が、どこかで交錯する鍵がないです。
それが事故に遭い、入院しているウィノナ・ライダーを見舞うところだったのか・・・
それともリリー(ミラ・クルス)とのセックスシーンなのか・・・
ちょっと判りません。
リリーとのセックスは、ホントのところは薬に酔ったニナが思い切り自慰した、ということなのですが、それもまた気の毒。
リリーめ、無理矢理やってやれば良かったのに・・・と思いました。
ニナに足りなかったのは、誰かとのめくるめくセックス。
実はそれだけ。
それにしてもバレエは美しいなぁ~。
日々の鍛錬があの舞台を作ります。
まさに選ばれた者だけが作ることができる、芸術です。
PR

|
05.10.15:29 野菜が育っている |
地震や原発の事故の経過を見ていて、緊急時にはお金よりも食料だな・・・「火垂るの墓」でも食料さえあれば清太さんとせっちゃんはあんな事にならずに済んだしな・・・と思うようになっていた。
そんな時にたまたま仕事で行った先が市民農園を運営しているNPO法人だったので、話を聞いているうちに気持ちに火がつき、即、契約してしまった。
素人ファーマーの出来あがりである。
広さ42㎡あるので、けっこう広い。
畝が6つできた。
そこでサニーレタス、ホウレン草、大根、にんじん、なす、しそ、トマトにカボチャ、スイカを植えた。
これが結構元気に育ってくれている。
レタス・ほうれん草・大根・ニンジンは種から植えたのだが、ニンジン以外はすでに2回も間引きして食べた。
もさもさ生えている。
はじめて間引きに行ったとき、ホウレン草と大根の畝にテントウムシがわらわらいるのに驚いて、こいつはもしか葉っぱ食べてんじゃ~?と敵意を燃やしたが、sacoさんらに話してみたらばアブラムシを食べてくれる良い虫だということが判明。
それが判った途端、初めてテントウムシを見つけたときの「あら~♪可愛いテントウムシ♪」という温かい気持ちが蘇った。
良い虫、良い虫・・・
自分で育てた野菜は美味い。
レタスもホウレン草もしゃっきりしていて柔らかい。
大根葉も、しっかり洗わないと葉っぱの裏に小さな卵がびっしりくっついていてゾワゾワするが、とても柔らかくて美味しい。
大根になるはずの部分も、まだ細かったけどしゃっきりしていて味があった。
なんせ私が愛するベビーリーフ(安いうえに量がかさむので野菜を食べた気になるから)を、「雑草みたいな味がする」「普通の野菜が食べたい」とうるさい娘が、間引いたホウレン草とレタスを美味しいと食べてくれたことが嬉しかった。
ここのところ雨が降る。
畑に水まきに行かずにすむので喜んでいる。
適度に雨が降り、お日さまが照る。
こういう天気が一番嬉しい。
きっと今日も野菜がわしゃわしゃ育っているはずだ。

|
05.10.10:10 ザ・ファイター ~映画~ |
1987フォーラムに書いたものに補足しつつ。
何がテーマなのかが判らない作品でした。
映画の中でもお兄さんのドキュメンタリーを撮っていましたが、作品自体がドキュメンタリーというか、ホームビデオみたい。
この作品の母親のような息子ラブお母さんは普通に日本の中でもわんさといる。
息子ラブというか、その実、自分の事が世の中で一番好きなんですが。
私事になりますが、マーク・ウォルバーグが母親に「僕だってお母さんの息子なのに」みたいな事を訴えて泣くシーンがあったが、弟が死んだ頃に私も同じようなことを母に言ったことがある。
ざっと見渡すと、世の母親は息子(それもひとりだけ)に対しては大なり小なり似たようなものじゃないか。
外国的(というか映画で知ってるアメリカ的)なのはお姉さんなのか妹たちなのか判りませんが、変な女の人たちがゴロゴロ同じ家に住んでいて昼間っからたむろってお菓子食べてたり・・・って姿にヤク中の兄、すぐにヒーローを作りたがるご近所さん。
この作品で何が言いたいのか、何が見どころなのか最後まで判りませんでした。
こういう家族がいましたよ、という記録映画。
この作品の母親が息子ラブ、というか娘たちに対してもあれだけの数が家の中にゴロゴロしているのだから、ほとんどネグレクトに近い。
子どもの面倒を見るとか甘いのではなく、見て見ぬふりではないか。
服装や髪形を気にしているところをみると(全然オシャレではないけれど)、自分に対しては気を使っている。
やはり自分のことが世の中で一番好きな女性。
とにかくその手の女性は世の中に掃いて捨てるほどいるので、別にめずらしくも何ともなく、そんな女性の尻にしかれながらもあんなにたくさん子どもを作っている夫がいて、息子ふたりがいろいろあったけれどボクシングで世界の頂点にまで登りましたよ、というちょっと不思議なお話なのであった。
お昼のメロドラマぽい。
ほんとにねぇ・・・・
ボクシングで頂点を取るって、けっこうスゴイことだと思うのだが、大したことないんじゃ?と思わせるところがボクシングファンとしては腹立たしい。
なおかつ、この作品が感動作のような扱いになっている雰囲気なのがわからない。
家族愛とか兄弟愛とか、この作品からはわからない。
少なくとも私には伝わらなかった。
何がテーマなのかが判らない作品でした。
映画の中でもお兄さんのドキュメンタリーを撮っていましたが、作品自体がドキュメンタリーというか、ホームビデオみたい。
この作品の母親のような息子ラブお母さんは普通に日本の中でもわんさといる。
息子ラブというか、その実、自分の事が世の中で一番好きなんですが。
私事になりますが、マーク・ウォルバーグが母親に「僕だってお母さんの息子なのに」みたいな事を訴えて泣くシーンがあったが、弟が死んだ頃に私も同じようなことを母に言ったことがある。
ざっと見渡すと、世の母親は息子(それもひとりだけ)に対しては大なり小なり似たようなものじゃないか。
外国的(というか映画で知ってるアメリカ的)なのはお姉さんなのか妹たちなのか判りませんが、変な女の人たちがゴロゴロ同じ家に住んでいて昼間っからたむろってお菓子食べてたり・・・って姿にヤク中の兄、すぐにヒーローを作りたがるご近所さん。
この作品で何が言いたいのか、何が見どころなのか最後まで判りませんでした。
こういう家族がいましたよ、という記録映画。
この作品の母親が息子ラブ、というか娘たちに対してもあれだけの数が家の中にゴロゴロしているのだから、ほとんどネグレクトに近い。
子どもの面倒を見るとか甘いのではなく、見て見ぬふりではないか。
服装や髪形を気にしているところをみると(全然オシャレではないけれど)、自分に対しては気を使っている。
やはり自分のことが世の中で一番好きな女性。
とにかくその手の女性は世の中に掃いて捨てるほどいるので、別にめずらしくも何ともなく、そんな女性の尻にしかれながらもあんなにたくさん子どもを作っている夫がいて、息子ふたりがいろいろあったけれどボクシングで世界の頂点にまで登りましたよ、というちょっと不思議なお話なのであった。
お昼のメロドラマぽい。
ほんとにねぇ・・・・
ボクシングで頂点を取るって、けっこうスゴイことだと思うのだが、大したことないんじゃ?と思わせるところがボクシングファンとしては腹立たしい。
なおかつ、この作品が感動作のような扱いになっている雰囲気なのがわからない。
家族愛とか兄弟愛とか、この作品からはわからない。
少なくとも私には伝わらなかった。

|
05.05.12:56 八日目の蝉 ~映画~ |
希和子(永作博美)は恋人の妻が産んだ子どもを衝動的に誘拐する。
あの赤ん坊が、あそこで泣き続けていたら・・・・話は変わるが、あの笑顔はCG?嘘じゃないかってぐらいの笑顔だった。
あんな風に笑顔を見せられたら、切羽詰まってる女性だもの、連れて行くわね。
その後、彼女が泣いてミルクを飲もうとしない赤ん坊に自分の乳を含ませようとする場面は、私が抱きしめてあげたいほど切なかった。
子どもを育てたことのある女性なら、あそこではきっとああすると思う。
そのシーンは、この作品の性格を表わしている象徴的な場面だと思う。
「それはないやろう」と思わせる演出がない作品だった。
言ってしまえば、あまりにも観客の気持ちに沿いすぎている。
上手に観客の気持ちの流れのまま流していって、ラストさくっと終わらせる。
とてもうまい構成だし演出だと感じた。
それは先日の「愛する人」の感想でも出したこと。
こういう作品群を観ていると、というか最近思うことでもあるが、女性が子どもを育てるために、はたして男性は必要なのか?
衣食住を維持するのにお金がいる。
その確保のためだけに男性が必要なのでは?と思ったりする。
ならば、女性が子どもを安心して預けて働きに出たり、休んだりできる環境があれば、男性はいらない。
男性はただの種でしかない。
この作品の男性の妻は、社会の仕組みの犠牲になっている、ひどく極端な存在だ。
何故にあれほど男に、いつまでも夫や父親としての義務を果たさせようとしているのか、私にはわからない。
夫に他に好きな人がいて、子どもまで出来たなら、あ、その女に行きなよ、って言やーいいのにと思うんだが(^^ゞ、世の中の女性たちは、「愛情の復活」だの「修復」だのを望んでまで一人の男と一緒にいたいんだろうか。。。。それはちょっともったいないぞ。
とにかく、その妻は、そんなもったいなく、その上そんな考え方しかできないから、自分で自分の首をしめている不幸な人である。
誘拐された赤ん坊はいつしか少女になり、産みの両親とともに暮らすようになるが、結局なじめず、一人暮らしをするようになる。
そして妻子のいる男の子どもを宿し、ひとりで母になる決心をする。
子どもはいつだって大人の顔色を見ている。
悪いことではない。
それは成長の過程で、当たり前のことだ。
だから大人から「すごいね♪」「がんばったね♪」褒められたら鼻をぴくぴくして自慢気に喜んでくれる。
注意したら素直にきく。
発達障害などの精神的な障害を持っていないかぎり、子どもはまず周りの大人との良好な関係性から自身を成長させていく。
友人との関係性をつくっていくのは、そのあとだ。
愛される=尊重される=敬意をはらわれる、ことだと私は思う。
愛することを甘やかすと勘違いしている人たちがいる。
こういう作品を観て、気付いてほしいなぁと思う。
与えられる愛は、物質的なものばかりではなく、深い記憶に残るものだということを。
人としての自信。
それはいくつもの記憶の積み重ねが作るのではないかと思う。
「八日目の蝉」というタイトルも、ホントやられた・・・くやしいほどうまい。
この作品を観る前に、偶然友人と東日本大震災の夜、空に満天の星空が広がっていたという被災者の話をしていた。
ああ、まさにそのことだなと思った。
良い作品でした。

|
05.03.23:52 素人なりにおもうこと |
ビン・ラディンが殺害されたらしいという報道。
いったいなんで今?
単純に、殺されたから報道されたのだろうが。
世界情勢には疎いのでそのあたりは判らないが、何かアメリカ国内で国民を鼓舞しなければならない事態か、目くらまししておかなければならない何かがあるのではないか?と思ってしまった。
何故、殺さねばならないのか?
殺したと報道しなければならないのか?
報復が恐ろしくはないのか?
もしか、何処かにわざと報復させようとしているのではないか?
そんなことを素人なりに考えてしまう。
近頃、「がんばれ」と言わない風潮になってきている東日本大震災。
ほんとに単純な国民だと思う。
もうひとつ形容詞をつけたかったが、あんまりなので我慢する。
どこそこのアーティストが言い出したとか、そんなことでしか判らないんだろうか、影響されやすいにもほどがある。
想像力があまりになさすぎる。
口蹄疫のときには、家畜のことを「牛さん、豚さん」などと言っていた畜産農家がいた。
可愛らしい絵になったり、これだけの家畜が殺された、とオブジェになっていたりしていた牛や豚や鶏。
口蹄疫だろうがなんだろうが、物ごころついた時から私は普通に牛や豚や鶏を美味しい、美味しいと食べている。
食べている肉は、殺された牛や豚や鶏だ。
ずっとそれらの死体を食べてきた。
牛の瞳が黒目で優しかろうが、それを食べて大きくなった。
屠殺場という言葉は差別用語になるそうだ。
食肉加工場といわなければいけない。
しかし牛や豚に「さん」付けは、ない。
いったいなんで今?
単純に、殺されたから報道されたのだろうが。
世界情勢には疎いのでそのあたりは判らないが、何かアメリカ国内で国民を鼓舞しなければならない事態か、目くらまししておかなければならない何かがあるのではないか?と思ってしまった。
何故、殺さねばならないのか?
殺したと報道しなければならないのか?
報復が恐ろしくはないのか?
もしか、何処かにわざと報復させようとしているのではないか?
そんなことを素人なりに考えてしまう。
近頃、「がんばれ」と言わない風潮になってきている東日本大震災。
ほんとに単純な国民だと思う。
もうひとつ形容詞をつけたかったが、あんまりなので我慢する。
どこそこのアーティストが言い出したとか、そんなことでしか判らないんだろうか、影響されやすいにもほどがある。
想像力があまりになさすぎる。
口蹄疫のときには、家畜のことを「牛さん、豚さん」などと言っていた畜産農家がいた。
可愛らしい絵になったり、これだけの家畜が殺された、とオブジェになっていたりしていた牛や豚や鶏。
口蹄疫だろうがなんだろうが、物ごころついた時から私は普通に牛や豚や鶏を美味しい、美味しいと食べている。
食べている肉は、殺された牛や豚や鶏だ。
ずっとそれらの死体を食べてきた。
牛の瞳が黒目で優しかろうが、それを食べて大きくなった。
屠殺場という言葉は差別用語になるそうだ。
食肉加工場といわなければいけない。
しかし牛や豚に「さん」付けは、ない。