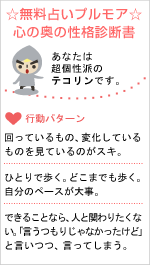|
02.23.08:24 [PR] |

|
12.10.19:10 無印良品ですがなにか? |
だいたい、どんな演奏会なのかを知らずに行ったのが間違いだった。
曲目はモーツァルト弦楽三重奏のためのディヴェルティメントK.563。
ブラームス、ピアノ五重奏曲作品34。
だいたいその曲目の時点でヤバイ感じがしたが、やはりジーンズ姿などで行ってる女性なんて私ぐらい。
あとは中学生の一団を連れた引率らしいお母さん、とかは服装にはかまってなかったな・・・・
とにかく、ちょっとドレスコードある?みたいな。
でもまあ、そこまでみすぼらしくも見えないだろう、と舞台から3列目の真ん中という困った席で聴いていたが、あまりに上品すぎてモーツァルトは思い切り寝てしまった。
モーツァルトが終わると、20分休憩、ということで、チケットをくれた義母系親戚と義父母、それに娘と一緒に会場内に用意されたカフェテリアに。
この義母系親戚はかなり苦手な部類で、ただニコニコして、「お久ぶりです。チケットありがとうございます」なんて挨拶して、コーヒーをおごられていた。
主催者側でもあった義母系親戚は、色んな人たちと挨拶したりして、またこれが「ちょっとセレブ」な感じでかなり居心地悪い。
で、一通り挨拶したあとでよそに行くこともできず彼女らが話している場にいると、あの人はいつも全身シャネルだ、あのお嬢さんはどこの誰それと今度結納らしい、副知事は良く顔を出される、など、たしかに演奏のことを言われても寝てしまった私だから全然相手にはならないので話が出なくてもいいんだけど、ついでにシャネルなんて名前は知っていても服なんて着たことないので、あ、私のコロンはエゴイストです、とは言える。
言わないけど。
で、振らなければいいのに社交術としてか、私が今夜着ていたマントは素敵ね♪など言われ、どこで買ったのか?と尋ねられてしまった。
ソニアリキエルです。
とは言えず、「無印良品です~♪」と本当のことを答えたが、絶句されたのは言うまでもない。。。
PR

|
12.05.22:40 母なる証明 ~映画~ |
~作品の中身に触れます~
 この母子関係は娘と母親ではあり得ない。
この母子関係は娘と母親ではあり得ない。
街中で、様々な人々の中で暮らしながらもひどく閉鎖的で濃密な母と息子の暮らしは。
息子を見つめる母親の視線は、無償の愛というよりも息子の心も体も、再び自身の中に取り込もうとするかのようにエロティックに感じた。
それは昔観た、新藤兼人の母と息子の近親相姦の映画のように、一見異常に見えるものをとても当たり前に。
息子(ウォンビン)には少し知的な遅れがあるのだろう。
母親(キム・ヘジャ)は漢方薬を売りながら、たまにヤミの鍼灸を行いながら、息子とふたり細々と生活している。
彼女の生活の全ては息子に向けられている。
未来を望むわけでもなく、ただ、その日その時、息子を愛おしいと思うことだけで暮らしている。
ある日、女子高生が殺害され、息子が逮捕される。
母親は息子の無実をかたくなに信じ、自ら事件の真相を追っていく。
冒頭、枯れ草の野原を歩いてきた母親が、BGMに合わせて踊り始める。
ポン・ジュノ監督は観客に、まずこの母親が愚かな女であることを知らしめる。
この作品は、彼女がどう愚かであるか、その証明であったようにも思う。
その愚かしさは、母と息子だが女と男である、という異性関係でなければあり得ない。
お互いへの強烈な依存。
そこに何の躊躇も疑問もない。
息子の無実を信じる、のではなく、ひたすら息子を信じているのだ。
その事を、ただ「愚かだ」とは言えない。
なぜならそんな関係は、日常的に男女間で行われているから。
この母親は、たぶん息子を得るまでは、周り全ての男にたいして依存していたのだろう。
昔から知り合いらしい刑事や、息子の友人など、もしかすると彼らとは肉体関係もあったのではないだろうか?そう思わせた。
そして、当然のことながら息子とも。
ねっとりとした「女としての血」「女としての業」、この動物的なエロス。
母親の恋人から虐待を受けて命を落とす子どもたちがいる。
母親も一緒になって子どもを虐待する。
その依存しあっている男女関係と、この作品の母子関係には何ら違いはない。
事件が図らずも一件落着し、平穏を取り戻したようにみえる母と息子だが、
「悪い出来事を忘れるつぼ」に自ら鍼を打ち、そして踊り始める母親の姿からは、母であり、女である愚かさを感じた。
ポン・ジュノ監督の前2作から感じた、静かな景色の中の虚しさ、孤独感、それらが今回は物悲しいタンゴに合わせて踊る母親の姿から、痛いほど伝わってきた。
それは母親という姿を借りた、「女」だからこその寂しさのようなものだろうか。
街中で、様々な人々の中で暮らしながらもひどく閉鎖的で濃密な母と息子の暮らしは。
息子を見つめる母親の視線は、無償の愛というよりも息子の心も体も、再び自身の中に取り込もうとするかのようにエロティックに感じた。
それは昔観た、新藤兼人の母と息子の近親相姦の映画のように、一見異常に見えるものをとても当たり前に。
息子(ウォンビン)には少し知的な遅れがあるのだろう。
母親(キム・ヘジャ)は漢方薬を売りながら、たまにヤミの鍼灸を行いながら、息子とふたり細々と生活している。
彼女の生活の全ては息子に向けられている。
未来を望むわけでもなく、ただ、その日その時、息子を愛おしいと思うことだけで暮らしている。
ある日、女子高生が殺害され、息子が逮捕される。
母親は息子の無実をかたくなに信じ、自ら事件の真相を追っていく。
冒頭、枯れ草の野原を歩いてきた母親が、BGMに合わせて踊り始める。
ポン・ジュノ監督は観客に、まずこの母親が愚かな女であることを知らしめる。
この作品は、彼女がどう愚かであるか、その証明であったようにも思う。
その愚かしさは、母と息子だが女と男である、という異性関係でなければあり得ない。
お互いへの強烈な依存。
そこに何の躊躇も疑問もない。
息子の無実を信じる、のではなく、ひたすら息子を信じているのだ。
その事を、ただ「愚かだ」とは言えない。
なぜならそんな関係は、日常的に男女間で行われているから。
この母親は、たぶん息子を得るまでは、周り全ての男にたいして依存していたのだろう。
昔から知り合いらしい刑事や、息子の友人など、もしかすると彼らとは肉体関係もあったのではないだろうか?そう思わせた。
そして、当然のことながら息子とも。
ねっとりとした「女としての血」「女としての業」、この動物的なエロス。
母親の恋人から虐待を受けて命を落とす子どもたちがいる。
母親も一緒になって子どもを虐待する。
その依存しあっている男女関係と、この作品の母子関係には何ら違いはない。
事件が図らずも一件落着し、平穏を取り戻したようにみえる母と息子だが、
「悪い出来事を忘れるつぼ」に自ら鍼を打ち、そして踊り始める母親の姿からは、母であり、女である愚かさを感じた。
ポン・ジュノ監督の前2作から感じた、静かな景色の中の虚しさ、孤独感、それらが今回は物悲しいタンゴに合わせて踊る母親の姿から、痛いほど伝わってきた。
それは母親という姿を借りた、「女」だからこその寂しさのようなものだろうか。

|
12.04.09:02 冬といえば |

|
12.02.23:46 空気人形 ~映画~ |
1987の映画フォーラムには書いたけれど、正直どう表現してよいのかわからず、ブログには手をつけられずにいた。
先週から宮崎でも公開になり、よせばいいのに今日、また観てきた。
表現の難しさの理由は、この作品に流れるいくつかのテーマが、あまりにプライベートな内容に触れるから。
性
快感(セックスもだが、日常の匂いや感触についての)
愛
孤独
空虚感
欲望
私は、文句なくこの作品が大好きだ。
なぜなら、この作品には映画としての醍醐味が全てある(全ては言いすぎだな、美男子はいなかった)。
私が伺い知らぬ世界、魅力的な女、美しくも悲しく残酷な愛の物語、心に残る言葉・音楽・景色、そしていつまでもあとをひく感情を教えてくれること。
大きく、二つのキーワードがある。
「代わり」と「からっぽ」
誰かの代わり、何かの代わり、そんなフリ、例えば嘘。
しょせん嘘でしょ?と言われたら、違うとは言えない。
「代わり」とは何と都合のよい、言いわけだろう。
もしかすると、嘘より誰かを傷つける言葉かもしれない。
それでもいいから、と、時に恋はそれさえも許してしまう。
その弱さ、脆さ、儚さ、切なさ、人の心とは愚かなものだ。
そんな愚かな心を持ってしまった「からっぽ」の人形。
ゴム製の、性欲処理の代用品。
中身はからっぽ、空気人形。
人を愛し、人とは違う自分を恥じ、出会うさまざま人々に自分は「からっぽ」なんだと話す。
すると誰もが応える。
自分もからっぽなんだ、君と同じなんだ、と。
心の空虚感はどちらも同じ。
寂しさも同じ。
からっぽの空気人形が抱えた空虚感は、とても重い。
しかし、彼女は無垢であったために、その空虚感は美しいものへと移り変わった。
どんな自分でもそのままに、寂しいまま空虚なまま生きていればよい、ということ。
道端のタンポポであっても風にのり、どこかへ繋がっていけること。
そしてそれは、ほんの少しの誰かの吐息であっても風の代わりに飛んでいき、どこかで誰かとつながって、わからない間柄であってもわからないうちに影響しあって、生き合っているのだということ。
みんなひとりぼっち。
そんな究極の「当たり前のこと」が表れているから大好きなんだと思う。

|
11.30.16:35 行ったり来たりすること |
色んな出来事もさることながら、11月の初めにたまたま見たそれは出来事ではなく、あの場所や展示されている内容からも人やモノや絵ではなく、タイトルにあるように「インタートラベラー(作者の造語)」気と気、空間と空間が交互に作用して行ったり来たりするものなのだろう。
「鴻池朋子展 インタートラベラー~12匹の詩人~」
霧島アートの森美術館で現在も開催されている展示で、私は彼女の作品群、彼女の言葉は視覚も聴覚もだ
例えば何かを表現する時、不思議なことに全てのものに名前があることに気付く。
ならば、はじめて言葉を発した人間はいったい何を語ったのだろう?
この広大な空間、美術館と森、その両方で私を迎えるこの奇妙な絵や、音や、弱気な顔をしたオオカミや、白い靴下に赤い靴の足から感じるエロティシズムは、私のどの部分で感じているんだろう。
そんなことをとても自然に思える空間で、その気持ちを私はまだ上手に言葉にできずにもやもやと、私の中だけに持っていた。
私は日常から離れることのできる時間、を大切にしていて、それは映画やひとりの車の中で聞く音楽などだが、そうできることをたまに、実はいけないことなのではないか?と考える。
秩序がひとつだけあるとすれば、それは生まれて生きて死ぬ、という生き物ならば当たり前の事実だけだ。
鴻池朋子氏の展示会では、そんな世界を目の前に見たような気がする。
オオカミの足は赤い靴をはいた少女の足、宙を舞う無数の短剣は卵を求める精子の群れ、またはたくさんの命、光や風や音や匂い。
一枚皮を剥げば、誰もが同じ形。
美しいものもみにくいものも。
内臓を通り骨が残る。
心だけは誰もが形を変え自由に飛んでいる、そんな世界。
本能と野生、それらはとても野蛮な秩序をもって存在している。
なんと残酷で美しい、すばらしい世界。
12月6日(日)まで、霧島アートの森美術館で開催中。
http://open-air-museum.org/ja/art/exhibition/konoiketomoko/
これは常設展示の作品。
素敵だった。