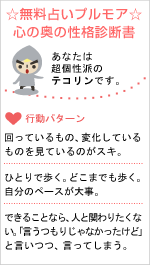|
09.02.21:40 [PR] |

|
12.17.13:30 この道は母へと続く |
ロシア映画です。
可愛くて素敵だった!
世界中の貧困国の孤児たちが、裕福な国のお金持ちに養子にもらわれているのですが(貧困国で、孤児で、とは限りませんが)、仲介する人によっては人身売買であったり、臓器売買であったり、という現実があります。
この作品は施設に預けられている子どもが養子が決まったけれど、「養子に行ったあとに母親が迎えにきたらどうしよう」と、本当の母親に会いに行く、というお話です。
施設には小さい子から大きい子まで年齢は様々で、大きい子は大きい子なりに施設の中で独立し、自分たちの生活を営んでいます。
そのたくましいこと・・・・・
女の子は売春であったり、施設の中で小さい子の世話をしたり、男の子はガソリンスタンドだったり、施設に来る養子仲介人の車の部品を盗んだり。
だけど、それがとても明るくてたくましい。
稼いだお金は皆で貯めてたりして。
ただ、こんな例えで悪いのだけれど、ペットショップの動物同様、小さい子じゃないと養子にいけないという現実がすごく悲しい。そして、そんな子どもたちが母親の存在を欲していることがつらい。
トラック運転手相手に売春しているイルカという少女が、主人公ワーニャに見せる母性がなんとも爽やかです。
それと、仲介人の運転手!
この人、いい!最後、すっげースッキリ!こーでなくちゃ!っていうか、判るよ!あの気持ち♪
つらい話題でもあり、考えるととても悲しい現実なのですが、そこに生きる子どもたちのたくましさがまぶしい、素敵な作品でした。

可愛くて素敵だった!
世界中の貧困国の孤児たちが、裕福な国のお金持ちに養子にもらわれているのですが(貧困国で、孤児で、とは限りませんが)、仲介する人によっては人身売買であったり、臓器売買であったり、という現実があります。
この作品は施設に預けられている子どもが養子が決まったけれど、「養子に行ったあとに母親が迎えにきたらどうしよう」と、本当の母親に会いに行く、というお話です。
施設には小さい子から大きい子まで年齢は様々で、大きい子は大きい子なりに施設の中で独立し、自分たちの生活を営んでいます。
そのたくましいこと・・・・・
女の子は売春であったり、施設の中で小さい子の世話をしたり、男の子はガソリンスタンドだったり、施設に来る養子仲介人の車の部品を盗んだり。
だけど、それがとても明るくてたくましい。
稼いだお金は皆で貯めてたりして。
ただ、こんな例えで悪いのだけれど、ペットショップの動物同様、小さい子じゃないと養子にいけないという現実がすごく悲しい。そして、そんな子どもたちが母親の存在を欲していることがつらい。
トラック運転手相手に売春しているイルカという少女が、主人公ワーニャに見せる母性がなんとも爽やかです。
それと、仲介人の運転手!
この人、いい!最後、すっげースッキリ!こーでなくちゃ!っていうか、判るよ!あの気持ち♪
つらい話題でもあり、考えるととても悲しい現実なのですが、そこに生きる子どもたちのたくましさがまぶしい、素敵な作品でした。
PR

|
12.17.13:26 2001年宇宙の旅~映画~ |
この作品、劇場で観て良かったっ!
今まで意味わからん!つまらん!と思ってたのは、テレビの小さい画面で観てたからだと判りました。
無理して時間つくってよかった♪
ここがこうでこうだからこうなんです、とハッキリ解説できはしないのですが、まず画面の構成がきれい。
全てのシーンがそのまま絵になる。
配色といい、置かれている風景や家具、壁、人、カンペキ。
これぞキューブリック作!
で、『ツァラトゥストラかく語りき』で始まるオープニングが鳥肌ものでした。
『美しき青きドナウ』で表される宇宙旅行、ただの息遣いのみ、の宇宙活動、美しい光線群・・・・・そのあとにやってくる無音の、そして美しいけれど牢獄のような真っ白い部屋。
胎児に返るデイブ、また流れる『ツァラトゥストラ』・・・・
ニーチェの言う超人の永劫回帰。
なんとなく判ってきましたよ。
第1章から、まずあの石碑は神を象徴しているのではないでしょうか。
恐る恐る触れた猿は道具を使うことを知り、動物の血を流すことを知り、そして争いで血を流すことを知る。
知能を持ったためにその罪を血で贖う、まさに『バベル』に出てきた血による贖罪の始まりです。
そう考えると、少し説明不足な感じはありますが、宇宙での船外活動で同僚を死に至らしめたデイブ、超人であることを誇っていたHALを消してしまったデイブ、そして多分彼の罪により未来へと続いていたはずの美しい光線群の先にある白い部屋は囚われの牢獄ではないか、と思うのです。
最後、胎児に返った彼ですが、それは私たち人間の罪の歴史は繰り返す、という意味かもしれません。
それはニーチェ=永劫回帰という考え方から、私が小さい頭で想像したにすぎませんが。
そうだ、確かにニーチェと神という考え方は矛盾してる・・・・
ま、とにかく劇場で観てない人は是非、観て損はなし!私ですら、眠くなりませんでしたよ。
HALはやっぱり可哀想・・・・・

今まで意味わからん!つまらん!と思ってたのは、テレビの小さい画面で観てたからだと判りました。
無理して時間つくってよかった♪
ここがこうでこうだからこうなんです、とハッキリ解説できはしないのですが、まず画面の構成がきれい。
全てのシーンがそのまま絵になる。
配色といい、置かれている風景や家具、壁、人、カンペキ。
これぞキューブリック作!
で、『ツァラトゥストラかく語りき』で始まるオープニングが鳥肌ものでした。
『美しき青きドナウ』で表される宇宙旅行、ただの息遣いのみ、の宇宙活動、美しい光線群・・・・・そのあとにやってくる無音の、そして美しいけれど牢獄のような真っ白い部屋。
胎児に返るデイブ、また流れる『ツァラトゥストラ』・・・・
ニーチェの言う超人の永劫回帰。
なんとなく判ってきましたよ。
第1章から、まずあの石碑は神を象徴しているのではないでしょうか。
恐る恐る触れた猿は道具を使うことを知り、動物の血を流すことを知り、そして争いで血を流すことを知る。
知能を持ったためにその罪を血で贖う、まさに『バベル』に出てきた血による贖罪の始まりです。
そう考えると、少し説明不足な感じはありますが、宇宙での船外活動で同僚を死に至らしめたデイブ、超人であることを誇っていたHALを消してしまったデイブ、そして多分彼の罪により未来へと続いていたはずの美しい光線群の先にある白い部屋は囚われの牢獄ではないか、と思うのです。
最後、胎児に返った彼ですが、それは私たち人間の罪の歴史は繰り返す、という意味かもしれません。
それはニーチェ=永劫回帰という考え方から、私が小さい頭で想像したにすぎませんが。
そうだ、確かにニーチェと神という考え方は矛盾してる・・・・
ま、とにかく劇場で観てない人は是非、観て損はなし!私ですら、眠くなりませんでしたよ。
HALはやっぱり可哀想・・・・・

|
12.16.21:12 靖国YASUKUNI~映画~ |
観てよかったです。
最初に出てきた右翼の人の檄文には共感できました。
8月15日に軍服を着て行進して御参りに来る人たち、彼らに至っても、アメリカの退役軍人パレードなんかに比べると実にささやかなものだと思うし。
南京大虐殺は捏造である、という考え方には賛成できませんが、そのあたりにしても私自身が歴史を知らなさすぎる、と思っています。
だから何とも言えません。
この作品を観る限り、靖国参拝に関しては戦争経験者や関係者ではない人たちがとやかく言えることなのだろうか?と感じました。
ただし、この考えも危険ではあります。
なぜなら、現在生きていて、元気にしているほとんどの日本人が戦争経験者ではないからです。
観ながら感じたのは、公平な歴史認識のない、そのほとんどの戦争不経験者たちがこれからの「靖国問題」を議論せねばならない状況にある怖さ、でした。
刀工の刈谷さんが「昔の強烈な思い出は?何か伝えたい思いはないか?」と尋ねられたときに、笑って何も答えなかったこと。
自分の作った軍刀で機関銃を切った、と教えてもらった、と話していたこと。
もっと色んなものを切ったことを聞いているでしょう。
そして、そう聞いたときに彼が何を感じたのかは決して第三者は判らないことです。
憤りだったか、それとも歓喜に似た達成感だったかもしれません。
でも、そんな気持ちはただの一般人である私たちには理解できないことです。
強烈な思い出や思いを、どんなに真剣に他人に語っても、聞いたその次の瞬間に他人は別のことを考える。
話すだけ無駄。
それを彼は知ってるのかもしれません。
目隠しして後ろ手に座らされた人に刀を振り下ろさん、とする軍人の写真。
首を持った軍人の写真。
そしてどこかの町に投下される爆弾の雨。
投下される原爆。
きのこ雲。
その一連の写真や映像には涙が溢れました。
いったいどこの誰が今にも目の前で殺されんとする人の写真を観て無感動でいられますか。
いったい日本人の誰が原爆を投下された映像を観て無感動でいられますか。
8月15日靖国神社の一日と、軍刀を打つことを仕事として誇りをもって過ごしてきた刈谷さん。
喧騒と静寂のコントラストに、戦争と思想と魂と神、それらに翻弄され続けている生霊のような日本人の姿がありました。
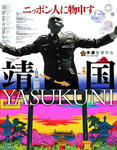
最初に出てきた右翼の人の檄文には共感できました。
8月15日に軍服を着て行進して御参りに来る人たち、彼らに至っても、アメリカの退役軍人パレードなんかに比べると実にささやかなものだと思うし。
南京大虐殺は捏造である、という考え方には賛成できませんが、そのあたりにしても私自身が歴史を知らなさすぎる、と思っています。
だから何とも言えません。
この作品を観る限り、靖国参拝に関しては戦争経験者や関係者ではない人たちがとやかく言えることなのだろうか?と感じました。
ただし、この考えも危険ではあります。
なぜなら、現在生きていて、元気にしているほとんどの日本人が戦争経験者ではないからです。
観ながら感じたのは、公平な歴史認識のない、そのほとんどの戦争不経験者たちがこれからの「靖国問題」を議論せねばならない状況にある怖さ、でした。
刀工の刈谷さんが「昔の強烈な思い出は?何か伝えたい思いはないか?」と尋ねられたときに、笑って何も答えなかったこと。
自分の作った軍刀で機関銃を切った、と教えてもらった、と話していたこと。
もっと色んなものを切ったことを聞いているでしょう。
そして、そう聞いたときに彼が何を感じたのかは決して第三者は判らないことです。
憤りだったか、それとも歓喜に似た達成感だったかもしれません。
でも、そんな気持ちはただの一般人である私たちには理解できないことです。
強烈な思い出や思いを、どんなに真剣に他人に語っても、聞いたその次の瞬間に他人は別のことを考える。
話すだけ無駄。
それを彼は知ってるのかもしれません。
目隠しして後ろ手に座らされた人に刀を振り下ろさん、とする軍人の写真。
首を持った軍人の写真。
そしてどこかの町に投下される爆弾の雨。
投下される原爆。
きのこ雲。
その一連の写真や映像には涙が溢れました。
いったいどこの誰が今にも目の前で殺されんとする人の写真を観て無感動でいられますか。
いったい日本人の誰が原爆を投下された映像を観て無感動でいられますか。
8月15日靖国神社の一日と、軍刀を打つことを仕事として誇りをもって過ごしてきた刈谷さん。
喧騒と静寂のコントラストに、戦争と思想と魂と神、それらに翻弄され続けている生霊のような日本人の姿がありました。

|
12.16.14:44 未来を写した子どもたち~映画~ |
「未来を写した子どもたち」~映画~
インドのカルカッタ、売春宿が立ち並ぶ場所に住む子どもたちが白人カメラマンのザナさんの写真教室で写真を学ぶ。
子どもたちの撮る写真はとてもユニークで、また奇跡のようで、彼らがもしもチャンスに溢れた街に住み、そのチャンスを生かせる立場にいるなら間違いなくいくつかの話題をさらい、未来へとつなぐことができるだろう。
しかし、彼らは売春婦の息子・娘たちで、住民登録もまともにとれず、学校に行くにもたくさんの書類が必要で、HIV検査は必ず受けなければならない。
普通に過ごしていれば男の子は麻薬中毒、女の子は売春婦になる運命にある彼らは、インドのカースト制度の中にも入ることのできないアウト・カーストと呼ばれる人たちなのだそう。
それにしても観ていてどうもスッキリしない気分だった。
それは、子どもたちにはまだ住む家がある、ということ。
また、寄宿舎のある立派な学校に入学できても、自らの意思で退学すること。
カメラマンのザナさんは西洋人としての思考で子どもたちを何とかしたい、教育を受けさせたい、チャンスを与えたい、と思っている。
入学に必要な書類集めも、どんなに面倒でもやり遂げる。
NYでの子どもたちの写真展も、カルカッタでの写真展も、才能ある子どもを大きな団体に紹介するのも、並みの情熱ではできないと思う。
だが、子どもたちの笑顔はとても素敵だった。
親元に置いていたら確実にお客をとらされるから寄宿舎のある学校に入れなければ、と奔走するザナさんだったが、この子たちは、自分たちを不幸だと思っているのだろうか?
そう感じた理由のひとつとしては、決して彼らが路上生活してる子よりもマシだから、などではありません。
救わねばならない可哀相な子どもたちには見えなかった、ということでしょうか、確かに住んでいる環境は劣悪なのですが。
私たちは私たちの尺度で彼らを見てはいけないのではないか?
少なくとも、この作品に登場した子どもたちに対してはそう感じた。
子どもたちの撮った写真はとても良かったです。
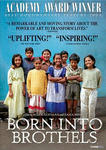
インドのカルカッタ、売春宿が立ち並ぶ場所に住む子どもたちが白人カメラマンのザナさんの写真教室で写真を学ぶ。
子どもたちの撮る写真はとてもユニークで、また奇跡のようで、彼らがもしもチャンスに溢れた街に住み、そのチャンスを生かせる立場にいるなら間違いなくいくつかの話題をさらい、未来へとつなぐことができるだろう。
しかし、彼らは売春婦の息子・娘たちで、住民登録もまともにとれず、学校に行くにもたくさんの書類が必要で、HIV検査は必ず受けなければならない。
普通に過ごしていれば男の子は麻薬中毒、女の子は売春婦になる運命にある彼らは、インドのカースト制度の中にも入ることのできないアウト・カーストと呼ばれる人たちなのだそう。
それにしても観ていてどうもスッキリしない気分だった。
それは、子どもたちにはまだ住む家がある、ということ。
また、寄宿舎のある立派な学校に入学できても、自らの意思で退学すること。
カメラマンのザナさんは西洋人としての思考で子どもたちを何とかしたい、教育を受けさせたい、チャンスを与えたい、と思っている。
入学に必要な書類集めも、どんなに面倒でもやり遂げる。
NYでの子どもたちの写真展も、カルカッタでの写真展も、才能ある子どもを大きな団体に紹介するのも、並みの情熱ではできないと思う。
だが、子どもたちの笑顔はとても素敵だった。
親元に置いていたら確実にお客をとらされるから寄宿舎のある学校に入れなければ、と奔走するザナさんだったが、この子たちは、自分たちを不幸だと思っているのだろうか?
そう感じた理由のひとつとしては、決して彼らが路上生活してる子よりもマシだから、などではありません。
救わねばならない可哀相な子どもたちには見えなかった、ということでしょうか、確かに住んでいる環境は劣悪なのですが。
私たちは私たちの尺度で彼らを見てはいけないのではないか?
少なくとも、この作品に登場した子どもたちに対してはそう感じた。
子どもたちの撮った写真はとても良かったです。