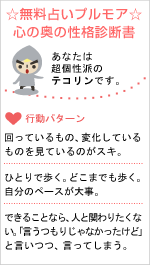|
08.24.14:27 [PR] |

|
06.16.01:23 明るい未来 |
良い出会いも多いけど、消えていった人たちも多い。
いなくなってみると、今までしょっちゅう鳴っていた着信メロデイが鳴らなくなって寂しいなぁ、とか、その程度。
だって会いたい気持ちがあるなら、私、自分から会いにいくもの。
別れたくなければ、いつまでもジタバタするもの。
別れたくなくてジタバタするほどの出会いは何年か前に気持ち使い果たした。
だからもういらない。
でも、そういうことがもしあったら?
るいさん、電話してくれてありがとう。
またふたりで愚痴りたい。
I believe I'm sure
I can do something for just love and peace.

|
06.15.02:07 Milk ~映画~ |
彼らがいったい何をしたというのだろう?
キリスト教はやっかいだ。
昔からホラー映画では、性について狂信的な家族の話が何度も取り上げられている。
同性同士の結婚について、ほとんどの反対者は熱心なキリスト教信者たちだ。
夕方観たNHKのニュースでは、アメリカの同性婚についての特集をやっていた。
反対していた人が、子どもを成すことのない自然の摂理に反した同性間の結婚など、神は許さない、と言っていた。
幸せな同性愛者は許されなくて、子どもを成す男と女なら、不幸な結婚でも許されるの?子どもができないと苦しんでいる人たちはどうなるの?
また、リベラルで公平であろう、とする人たちの中にも、どこか勘違いがある。
同性愛者に関する科学的なデータが出た場合、それを身近な同性愛者に語りたがったり、何とか自分自身の考えの中で理解しようとしたり。
無理だから、関係ないから、そんなこと。
でも、無関心じゃないだけいい。
それはやはり、先人たちの導きや活動があったからだろう。
そのひとりがハーヴィー・ミルクだ。
彼は隠すより表に出すことで、社会に知らしめようとした。
また、政治的に他のマイノリティたち(黒人や障害者や社会的弱者と呼ばれる人たち)と結びつけて戦ったことが画期的だった。
「Milk」という作品の中で、彼が破棄に力を注いだ条例6(教職にあるものの性的指向により解雇できる)、これは随分とあまりな話ではあるけれど、これは性的指向が性的嗜好と同じように語られる社会的な勘違いも大いに関係する。
同性愛は性的指向(髪の長い色白の女性が好きとか、そういうこと)であって、性的嗜好(SMや幼児性愛など)とは違うが、昔から男性同性愛者の中には幼児を対象にする人がいることも事実。
この作品は彼が凶弾に倒れるまでの活動を淡々と描いている。
アカデミー脚本賞を受賞したが、私はそこまで脚本が素晴らしいとは感じなかった。
きっとマジョリティは内容がどう、という話はできないだろう。
ハーヴィーの人となりを語るにしても、一生懸命戦った姿はわかるだろうが、それ以上のものを感じることはできないだろう。
ゲイとレズビアンが手をとって戦ったことが画期的だったことも、わからないだろう。
それはやはり同性愛の特異性に目を奪われ、そちらを印象的に感じるから。
ただ、いつもは無表情であまり笑わないショーン・ペンが、とても愛嬌ある演技を見せてくれていたこと、効果的に使っていたオペラの「トスカ」、ハーヴィーがこのオペラを観て、失った恋人に早朝、電話をするシーンからは、誰かを愛する気持ちは異性愛だろうと同性愛だろうと関係ない、と思える。
あの時の彼の孤独、喜びには胸を打たれる。
その後の展開が切ない。
「トスカ」のポスターを見るハーヴィーの目に、それ以上に映っていたもの、を思うと胸が痛い。
40歳になっても何もできなかった、そう言うハーヴィーがそれからの8年間でやったこと。
それは現代アメリカに力強く息づいていると思いたい。
ハーヴィーを追悼しようと多くのマイノリティが灯をともし、行進した、あの、光のミルキィ・ウェイは美しかった。
黒人大統領が生まれたように、決して彼がやったことは無駄ではなかった。

|
06.14.02:01 大丈夫であるように。 |
今回もいくつかのはじめましてと、さようならがあり、気持ちの切り替えが得意ではない私は、今すごくまいっている。
もしかすると、もう二度とは会えないかもしれない人たち。
彼ら彼女たちと、もう少し一緒にいたい、もっと知り合いたい、と思うほどに、会えないかもしれないなら思い出が増えるのは悲しくて、できるならちゃんと「さようなら」はせず、早くその場から逃げたいと思った。
遠いところに住む人たちとの別れはいやだ。
帰ってしまうと思うのがいやだ。
気楽に立ち回れば良いのに、そう思えない私がいやだ。
いちいち感じてしまう、小さい私がいやだ。
だけどそう思ってしまうから、しばらくはこんな気分で、思い出しては泣きそうになる心と付き合うしかない。
最後に観た作品は是枝裕和監督のドキュメンタリー『大丈夫であるように―Cocco終わらない旅―』。
ほんの数年前に初めて聴いた彼女の歌が「強く儚い者たち」。
耳触りのよい曲で、ふんふん・・・と聴いていると、ずどんと奈落に落とされる。
こんな歌詞を書く人だから、きっと生い立ちに何らかの影を持っているのだと思っていた。
作品の中に彼女の父親や母親がでてきて、それが間違いだったとわかった。
それで彼女をますます好きになった。
この人も普通なんだ。
私たちより正直なだけなんだ。
それを表現して生きていたから表現者になり、自分以外の周りの思いも正直に受け止めて抱え、折れながらフィックスしながら立ってようとしている女性なんだ。
砂浜でファンレターを燃やしていた。
そうだよ、失くしたほうがいいよ、と思った。
手紙や絵や贈られた何もかもが赤々と燃える炎の中に、彼女は自分の髪の毛を切って落とした。
長かった髪の毛は肩までになった。
彼女の『Raining』のようだと思った。
贈ってくれた人たちの一生懸命に、彼女は自分の一生懸命で最後も応えた。
是枝監督はドキュメンタリー出身の監督だからか、対象のcoccoに上手に寄り添いながら作っていた。
ライブの模様がほとんど、移動の車の中、彼女が訪れた場所、彼女の歌、この作品用にしっかりと彼女をとらえて話を聞いたシーンはたった一か所。
彼女は宮崎駿の『もののけ姫』を例に話す。
いままではラストに少しの希望をもたせて終わるのはダメだ、わからない人たちにわからせるには全てを破壊して危機感を持たせないとダメだ、と感じていたが、子供と一緒に観たときに、「お願いだから最後に希望をもたせて」と祈った・・・と。
子供たちには希望を、明るい未来を見せてあげたい、そう願ったと。
それが10代の頃と、子供を持ってからの違いだと。
メジャーデビューして数年の彼女の歌と、子供を持ってからの歌はまるで違う。
なぜそうなのか、母になった人にはわかること。
「子どもには希望を・・・」と思った彼女の気持はとてもシンプルで、すごく素敵で、私も娘にそう感じたことに花丸のハンコをつかれたような気分だった。
気にせずに言いたい。
これが、子供を持った女の良さなんだぞ、と。
coccoは荷物を抱えて生きることにすごく正直に真っ直ぐに向かい合っている。
その健気さが痛々しいけれど、そんな生き方をしている彼女以外の人たちのためにも今回のドキュメンタリーで、あえて自分をさらしてくれたのかな、と感じた。
それが表現者としての立場で、同じ折れそうに生きている人たちへの「お互い、大丈夫であるように思ってる」んだよね、という控え目だけど心に響くメッセージなんだと。
このドキュメンタリーの写真集『大丈夫であるように。-Cocco終わらない旅‐』。
その中に書かれてある一遍の彼女の言葉
憎いと思っても 一度もあなたを愛さなかった瞬間など ない。
他のどんな言葉よりも、その思いが何よりも私の中ではまって刻まれて、なぁんだ、偉そうなこと言っても結局はそれだけじゃない、そう誰かに思われても、、、、、、
でもね、だってそうなんだから。
そしてそう気付くことが、自分を癒す薬になっていることを、きっとCoccoは知っている。

|
06.12.00:27 ひとつづつの そしてひとつの |

|
06.11.01:35 つきあってくれた |
『接吻』のラストについての解釈を色んな人たちが話している。
何人か共通しているのは
「京子(小池栄子)は長谷川(仲村トオル)を愛しはじめていた」
『接吻』ネタバレしてます。
長谷川は京子に寄り添おうとしていた。
その気持ちをありがたいと感じながらも、京子は自分とは違う人間だと長谷川を見ている。
「たったひとりだけじゃ死刑にはならないんでしょ!」
そう叫びながら彼女は長谷川に向って行き、キスをする。
そのキスを私は儀式だと思ったけれど、彼を殺さずに生かしておいたことで、あの作品には未来への希望が少しだけ残っている。
京子は長谷川に心を許していくかもしれない。
どうしても私が長谷川への京子の愛を感じなかったのは、あれだけの孤独を抱えている人が、初めて自分に寄り添おうとしてくれた人に、恋愛感情を抱くか?という疑問からだ。
私だったら、という極個人的な意見だと、NOだ。
恋愛感情ではなく、家族愛とか、強い友情のようなもの、同志的な感情なら感じる。
私の場合だと、好きで好きでたまらない人がいて、その人に自分を否定されたり拒否されたときや、声をききたくてたまらないけど連絡もままならない、我慢しなければいけない、と自分を律するとき、または他の誰かからの心無いひとこと、態度などをみて、自分自身を理解してもらえない、と感じたときに孤独を感じるので、原因がハッキリしている意味で京子のものとは違う。
京子の場合は、随分と独りよがりだ。
上手に立ち回れない、自分の気持ちを外に出せない、だから友だちもいない、というのは自分自身の問題だし卑屈だ。
彼女はネットを利用してはいなかったけれど、もし利用していたら秋葉原での凶行に至った彼と、そう大差ないのではないか。
あの彼とも違うのは、京子は自分自身を理解してほしい、と周りにサインすら出していないこと。
頑なに「私のことを理解する人はいない」と、思いこんでいる。
孤独を感じる心は理解できるし共感するけれど、京子が感じている孤独は、あまりにも漠然としていて実体がない。
実体がないから恐ろしいし、寄り添えない。
長谷川にしても、始まりは職務から。
そのあとは同情か、興味か、なんとなくだが軒下に住みついてしまった子犬か子猫に餌をやるような気持ちに少し似ているかも・・・と思う。
そんな京子の自分勝手な気持ちに付き合わされた坂口(豊川悦司)にしてみたら迷惑な話。
しかし、かなり奇妙な怪我の功名だけれど、崖から飛び降りた先に大きな鷲の巣があって、母鷲がひなと間違えて餌をせっせと与えるような、そんな不思議な居心地の良さの中で、自分の犯した罪の大きさを感じるようになるのは皮肉だ。
しばらくすると、餌を運んでいた母鷲は、それが自分のひなではないことに気付く。
多分そうなるだろうこと、彼は知っていたはず。
京子の独りよがりな気持ちを受け入れていたのは、彼には失うものが何もないから。
自分とは違う人間性を感じながら付き合っていたのは、彼もまた「もう、何もかもどうでもいい」人間だったから。
勘違いでも自分を真剣に思ってくれた相手から殺されるなら、それ以上の幸せはない。本望だろう。
もし京子に寄り添ってくれたのが長谷川ではなく、新興宗教の人なら、彼女は強力な信者になるだろう。
あのような、自分は神に選ばれた特別な存在であるかのように勘違いしている人ならばなおさら。
彼女の孤独から感じた潔さのようなものは、自分でそうあろうと決めている、信じている姿から表れている。
実はひどく単純だからこそ彼女はあのあと、長谷川に心を開いていく可能性があるように思う。
彼女の長谷川への接吻は、自分以外の外の世界への最後の抵抗でもあり、扉でもある。