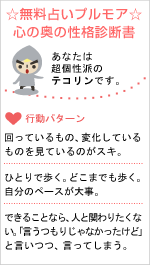|
12.14.01:18 [PR] |

|
06.07.21:14 その土曜日、7時58分 ~映画~ |
一応私の居場所でもあるシネマ1987が発端となっている映画祭なので、何人もの映画仲間が実行委員で頑張っている。
いろいろと運営方針やラインナップ決めでの葛藤はあるようだが、なんだかんだ言って実行委員やってる人たちは私の大好きな人たちだし、毎年楽しみにしているお客さんは大勢いるし、続いていけばいいなぁ!と思う。
初日に観たのが
『その土曜日、7時58分』
ラストに触れます。
会社のお金を横領していた兄、離婚した妻への慰謝料や娘の養育費に首が回らない弟、兄は両親が経営する宝石店に強盗に入る計画を弟に持ちかける。
計画は完璧だったはず。
弟が強盗役を他人にまかせなければ・・・・
兄はフィリップ・シーモア・ホフマン、弟はイーサン・ホーク。
最初は胡散臭いだけの兄だが、彼がドラッグに溺れている描写から、作品はだんだんと彼の色に染まっていく。
彼が持っていた弟への嫉妬や両親への不信感。
弟と浮気をしていた妻。
それらが露わになっていくとき、今までの冷静で人を小バカにしていた彼の本当の姿が見えてくる。
彼はほんの小さな、小さな少年。
両親の愛を感じられず、悲しいと泣くこともできず、ただ自分をしっかりと見せることで必死に生きてきた。
兄の最期で疑惑は現実味を帯びる。。。
フィリップ・シーモア・ホフマン、彼の色の白さと髪の毛で、いつもカーネル・サンダースを思い出すが、私はこのオカマっぽい中年が妙に気になる。
彼の寂しそうな表情には胸が締め付けられる。
何もかもわかって、呆けたような表情には胸が痛かった。
ああ・・・あんな顔、私もどこかで見たような気がする。
ドミノ倒しのように崩れていく彼らの人生。
それは兄の弟への嫉妬が引き起こした事故だ。
まるでカインとアベルのように。
兄は弟に強盗をまかせてはいけなかった。
彼はどこかで弟が銃で撃たれ、死ぬことを望んでいたのではないか?
その思いが彼を破滅へと動かしていった。
心地よいほどの転落・・・
だれもが奈落へ落ちていく。
それは彼らの心の闇が作った地獄。
こんな洋画、久しぶりに観た。
フィリップ・シーモア・ホフマン、ただの太っちょじゃない。セクシーだと思った。

|
05.26.01:25 コリントの信徒への手紙 13章 ~愛のむきだし~ |
愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。
愛は決して滅びない。預言は廃れ、異言はやみ、知識は廃れよう、わたしたちの知識は一部分、預言も一部分だから。完全なものが来たときには、部分的なものは廃れよう。幼子だったとき、わたしは幼子のように話し、幼子のように思い、幼子のように考えていた。成人した今、幼子のことを棄てた。わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、鏡と顔とを合わせて見ることになる。わたしは、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られているようにはっきり知ることになる。それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。』
すごく好きだった言葉。
ユウのヨーコへの気持ちに嘘はないとしても、彼の行為は愛情の押し付けでしかない。
新興宗教から彼女を救うため、だとしても。
考え方がとても難しい。
私は太陽や月や山や海などの自然にたいしての畏れや畏敬の気持ちは持っているが、それを語る人間の誰かを信仰はしない。
しかし、それをやったことで自分の苦しみから解き放たれたり、救われた、という人に対してどうこう言うつもりもないし、私や私の周りに迷惑がかからない限りはその人もその宗教もそのままで良いと思っている。
オウム真理教のように社会に対してテロ行為を行ったり、殺人を犯したり、ではない限り、(ごめんなさい、もし信仰している方がいたら申し訳ない)創価学会だって立派な新興宗教で、あからさまな勧誘行為だってやっているし、入会して、今まで家にあった仏壇や位牌を捨て、学会のための仏壇を買ったり、などという家族もいる。
話が横道にそれたように思うが、「愛のむきだし」という作品について考えたとき、「カルト的宗教」というものを絡めず物語を作ったらどうだったのだろう?と、ふと考えた。
今はまだ頭の整理がついていないので、また、そのうち。

|
05.19.01:01 エレジー ~映画~ |
著名な大学教授が美しい教え子に恋をする。
彼は別れた妻との間に医師をしている息子がひとり。
恋人とは呼べないが、好きなときにやってきて、そして軽くセックスを楽しむだけの女友達もいる。
なんでも話合える友人もいる。
好きでひとりでいるし、彼の人生はパーフェクトのように思えていた。
彼女に出会い、恋に落ちるまでは。
ネタバレします。
教授は30も年下の彼女に対して保護者のような、人生の教師のような、そんな立場をとっていたが、彼女には彼が経験したことのないセックスや歴史があったことを知り、己の自信がだんだんと崩れていく。
崩れた「自信」、それは実にたわいもないことであり、傷つく自体馬鹿馬鹿しいこと。
しかし保護者的立場だった彼には「自分の知らないことを知っている」ことがどれだけ重かったか。
生身の女性なのだ、と知ったとき、「芸術品のよう」な彼女はもっと光り出す。
いつもそばで見ていなければ心配なほど。
誰かにとられはしないか、誰かを好きになりはしないか・・・・と。
そんな嫉妬にさいなまれる情けない彼を、彼女は受け入れる。
それで良いはずなのに、彼にはもうひとつ、最初から持っていた負い目がある。
30歳という年齢の差。
彼女は美しい若者だが、自分は醜い老人だ、と。
絶対的な負い目を持ちながら恋をはじめる。
もしかしたら自分を許してくれるかもしれない、という甘えもある。
その気持ちはわかる。
真剣なんだ、ということも。
相手に対して負い目があるなら、はじめから声をかけちゃだめだ。
それもわかる。
だけどもしかしたら上手くいくかもしれない・・・
そうして始まった恋は、彼女もずいぶん上手(うわて)で、余裕があったはずの彼はいつの間にかその恋に深くハマってしまう。
もうひとり、長年の女友達。
彼女はまだ歳も近く(といっても10歳以上は離れているだろうが)、軽くセックスだけなので気軽。
年下の彼女はいつ自分を捨てるかわからない。
寂しいので、彼女には居てもらわないと困る。
だから美しく若い女を抱いたあとでも彼女を抱く。
このずるさ。
けど、わかる。
彼の息子には愛人がいる。
息子は本気で愛人を愛していることに苦しんでいる。
妻や子供に対しても誠実であろうとして、苦しんでいる。
これもよくわかる。
様々な恋愛模様がとても切なくて、そして悲しいほどに不器用で。
相手に対しての負い目や甘えのある恋、家庭を持つものの恋、それらに対して答えはないけれど、どこか希望を感じさせる大人の恋愛映画でした。
エンドロールが素敵だった。。。とっても。

|
05.17.02:30 永遠のこどもたち ~映画~ |
過去、現在、未来・・・
そのいずれにも「永遠」はある。
幸せな孤独。
そんな言葉をちょっぴりあてはめてみる。
以下、思い切りネタバレしますので、これから観ようと思っているなら読まないほうがよいです。
孤児院だが仲の良い仲間たちがいて、きっと幸せに過ごしていたのだろう。
結婚した彼女は、そこを障害のある子供たちの施設にしようと家族と移り住む。
ひとり息子のシモンには空想の友だちができ、不思議なことが起こるようになり、開園準備の中、シモンが忽然と姿を消す。
ニコール・キッドマンの「アザーズ」のような雰囲気。
孤児院の建物も古くて広い建物。
怪しいソーシャル・ワーカーや、見えない何かに立ち向かう母親、という設定も。
違うのは、息子の秘密や孤児院での秘密、息子の最期などが実にさりげなく普通に登場すること。
ただし、その演出が緊張感にあふれ、とにかく最初から最後まで一気にみせる。
残酷なシーンは一か所ぐらいで、それも怪我をした、とかそういうこと。
なんといってもこの作品で秀逸なのは、ラストのラウラと子供たちのシーン。
あのシーンの感動は、あとからあとから止めどなく打ち寄せる波のよう。
「アザーズ」のようにただ切ないだけでなく、もしかするとハッピーエンドなのかも?とも思う。
そこにはあまりにも切実な「永遠」があるから。
最終の回で観たのですが、帰りの自転車からみた大淀川の景色がとても綺麗で、切ない気持ちになりました。

|
04.27.21:25 グラン・トリノ ~映画~ |
ラストが救いようがなくて、いつもいつも女性がどこか悪いイメージで、良い映画だとは思っても、好きにはなれなかった。
『ミリオンダラー・ベイビー』を観るまでは。
『グラン・トリノ』
ネタバレします。
偏屈なウォルト。
彼は朝鮮戦争帰り、その後結婚、アメ車工場で定年まで働き、子どもらは独立、妻に先立たれてからは芝生を刈って、自慢のフォード・グラン・トリノを磨いて眺めながらビールを飲んで過ごす。
それが至福のとき。
差別主義者の彼だが、グラン・トリノを盗みに入ってきた隣家のアジア系移民の少年や、少女、その家族との交流がはじまる。
戦争で無意味で残酷な殺人を犯したことが大きな心の傷になっているウォルトは、彼に無限の明るい未来を見たのではないだろうか。
タオ少年や、聡明で明るい姉のスーと触れ合ううちに、ウォルトの心の壁はさらさらと取り払われていくが、しつこく絡んでくる彼らの従兄弟たちの存在が暗い影をおとす。
その従兄弟たちのひとりをブチのめした報復で、スーを輪姦されたウォルトは、ある選択をする。
イーストウッドによるイーストウッドのイーストウッドのための映画。
と言えばあんまりだろうか。
とにかくイーストウッドの男っぷりが良すぎる。
ぶつぶつ文句は言うが、正直なだけで心根は優しく、そして慎み深く、心に傷を負いながらも平和に生きている。
年老いて、妻はいないし、どうやら命に関わる病があるらしい。
命の期限をたぶん彼は知り、そして自分が最後にやるべきことを考えた。
それは、隣人の少年・少女を守ること。
自分の中で、戦争で殺してしまった人々への贖罪を行うこと。
そして気持ちのどこかには、生き方がすれ違ってしまった息子への抗議や、そう育ててしまったことへの自身のケジメもあったのではないだろうか。
丸腰でギャングたちの前に立ち、銃弾に蜂の巣にされた彼は、まるで大きな十字架のように倒れていく。
このラストだが、大きいというか格好良いというか、正義や赦しとは・・・などと考えさせられる。
タオ少年に託されたグラン・トリノが、アメリカという国の新しい可能性、を感じさせる。
大きな愛をもらった気になる。
だが、それは彼の死をもってしか表すことはできなかったのだろうか。
彼の持っていた大きな愛。
大きな心。
それらを、生きて伝えていくことはできなかったのだろうか。
あれは立派な自殺ではないか。
老醜をさらしてもいい、それでも生きていてくれさえすればいい。
私にはそれがどうしても解せない。
生きていてほしい。
あれはだめだ、自殺はだめだ。
ちゃんと動けるうちに自分の男らしさの美学を完結させたかった、そういうことか、と。
どうしても素直に感動に浸ることができなかったのは、「ミリオンダラー・ベイビー」の時と同じく、イーストウッドの年老いた顔かたち、姿かたちが父によく似ていたから。
スーと話をする姿や、スーが輪姦されて帰ってきた姿を見た彼の表情などは、父を見るようでいたたまれなかった。
父が傷ついたようで、それがとても悲しかった。
だめだ、お願いだから生きていて、生きてるだけでいいから、と、願いながら観ていた。
あんな死に方してほしくない。
置いていった十字架が重い。
大きすぎる。
結局、やはり彼は孤独だったのだ。
彼の自死に心から傷つく人が、もうこの世にいなかったのだ。
だから彼にはあの選択ができたのだ。
素晴らしい作品だと思ったが、私には重かった。